不都合な事実と向き合うための作法
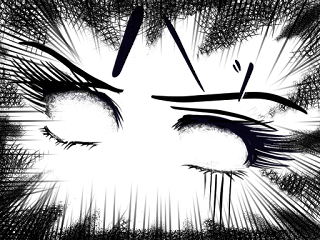
前回の記事 で、見たくない不都合な事実と向き合っていくためには、何か作法のようなものが必要ではないか、と書いた。では、どういった作法であれば、不都合な事実と向き合っていくことができるだろうか。まずは、思いつくままに書き出してみたい。 ●不都合な事実と向き合うための作法 ・自分は見たいものだけを見てしまうものだと自覚すること。 ・見たくない事実を見るには、自分だけでは無理だとわきまえること。自分だけに抱え込まず、他者と共有して考え合い、団体の場合は、問題を団体の外に開いて考えること。 ・被害の訴え、問題指摘、批判などに対しては、脊髄反射的に否定しないこと。できるだけ予断なく、虚心坦懐に話を聞くこと。また、自分の価値観で決めつけないこと(それぐらいたいしたことない、など)。 ・被害の訴えなどのあった場合、安易に被害者の心理や認知の問題にしないこと。 ・自分も「まちがっているかもしれない」というわきまえを持ち、自分の感覚をあたりまえにして押しつけないこと。 ・客観・中立を装わないこと。どんな場や人間関係にも力関係があることを踏まえ、常に力関係の弱い側に立とうとすること(客観・中立の態度は、力関係の強い側に立つことになりやすい)。 ・大義や大きな目的のために、足下で起きた問題を抑圧したり軽視しないこと。 ・自分の意識を世間のほうに向けないこと(評判リスクの問題にしないこと)。 ・「まさか、あの人が」バイアスに要注意。「仲間」の問題を見て見ぬふりをしないこと。 ・問題と人格は分けること。人格をおもんぱかって、その人の起こした問題を見ないことにしたり、逆に、問題を起こした人の人格を否定して、排除するだけにしないこと。 ・問題を起こさないように管理するだけではなく、問題が起きたときに否認せず、きちんと対応できるように考えること。 ・かといって、問題だらけでOKと開き直らないこと。 ・日ごろから、他者からの批判、異論、ノイズなどを大事にすること。自分のいる場の同調圧力、ウチ意識、権力性をゆるめておくこと。個人が自分の意見を言いやすい風通しのよさを心がけておくこと。 * * * よくある行動指針や倫理規定などのガイドラインは、問題が起きることの予防を目的に、禁止事項を盛り込んでいることが多いように思うが、ここに挙げたのは、何か起きてしまったとき、それが自分や自分のかかわる団体にと...
