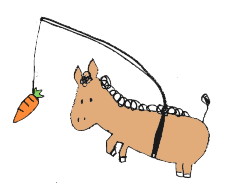教育機会確保法成立後の悪夢的状況について

12月9日に超党派フリースクール等議員連盟の総会が開かれたそうだ。出席した鳥羽恵さんが、 ブログ にその感想を書いているが、経産省が主導権を握って話を進めているようすがうかがわれる。以前から懸念していたことが、ますます進行しているようだ。あらためて、教育機会確保法成立後の懸念について、ここに書いておきたい(以前に書いたことと重複している部分もあるが)。 ●「未来の教室」が目指すものは 教育機会確保法は、提案された当初から、義務教育を民営化していくための規制緩和になるのではないかとの懸念が強くあったが、法案が審議されている過程では、NPOのフリースクールや夜間中学校などを支援するものとして謳われていた。しかし、法律施行から1年ほど経った2018年あたりから、教育産業がこの法律を活用しようとする動きが次々と出てきた。たとえば、2018年に立ち上がったクラスジャパンプロジェクトは、「学校・企業・地域が一丸となって不登校の小・中学生を支援するプロジェクト」で、自宅にいながらITを活用した学習支援などをするという(ネット教科学習、ネット担任、ネット部活など)。同プロジェクトには、N高校を設立した角川ドワンゴ学園の理事や元ベネッセコーポレーションの理事などが名をつらねている。そして2019年5月には、「 クラスジャパン小中学園 」を開校すると発表した。 また、同じく2018年に開始された palstep は、「不登校や学びにくさのある児童生徒の学習支援」を謳うeラーニングシステムで、「これまで難しかった不登校児童生徒の評価が行われることを目指し」「児童生徒の健康状態、生活習慣、学習習慣などがコミュニケーションボットのログや学習履歴からデータとして蓄積されることにより、これらを活用してさらに適切な支援計画や授業計画の立案を行うことが可能」としている。運営するのは、ソフトバンクグループの株式会社エデュアスだ。 ほかにも、家庭学習をITで行なう民間の教育サービスなどが次々に活動を始めており、それらは「EdTech」と呼ばれている。2018年には、経済産業省が「 未来の教室実証事業 」を始め、EdTechの事業者を公募、これまで81の事業が採択されている(2020年12月現在)。また、コロナを機に、 EdTech導入の補助金 も出されている。 ここでは、どういったことが目指されているの...