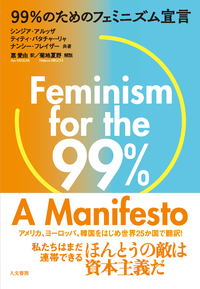目の前の問題に閉じ込められずに
不登校について、「二重の疎外」という視点を入れると、見えてくるものがある。 以前にも書いた ことで、疎外という言葉はいかにもいかめしいのだが、あらためて少し考えてみたい。 「二重の疎外」というのは、社会学者の見田宗介が言っていたことで、「貨幣への疎外」があって、「貨幣からの疎外」が問題となるということだった。人がお金でしか生活できない世界に投げ込まれてしまうと(貨幣への疎外)、お金がなくなること(貨幣からの疎外)が生死にかかわる問題になってしまう。 これを学校にあてはめても、同じことが言える。「学校への疎外」があって、「学校からの疎外」が問題となる。学校へ行かないと就職が困難になってしまう世界(学校への疎外)では、不登校(学校からの疎外)が問題となる。不登校が問題とされてきたのは、そもそもは人びとが学校へと疎外されてしまっているからだと言える。 しかし、多くの場合、学校への疎外は意識すらされていない。お金を稼がないと生きていけなくなっていること(貨幣への疎外)が、おかしいとは思えなくなっているのと同じように、学校に行くことは疑われることなく、そこに行けなくなることの不利益ばかりが問題にされてきた。 不登校の当事者運動では、学校への疎外を問うていた面もあったように思う。あるいは、「オルタナティブ」という言葉も、学校への疎外に対するオルタナティブを求めていた面もあったように思う。しかし、だんだんとその問いは後退して、いまや学校への疎外を前提としたうえで、その学校(教育機会)を多様化することばかりが言われるようになった。ただ、いくら学校(教育機会)を多様化しても、学校への疎外(「教育への疎外」と言うべきかもしれない)はますます徹底され、その苦しさは深まるばかりだろう。 ここまでは、 以前にも書いた 。もう少し考えてみたい。 ●ドリーム、イマジン、対話 教育機会の多様化というのは、いまの社会のあり方をそのままに、そのなかで個人が能力を磨いてがんばるためのものだと言える。つまり、個人モデルだ。あるいは、貧困問題で学習支援の必要性が言われる場合も同じだろう。個人モデルは、個々人にとっては必要な面もあるとは思うが、根本的には社会を変える力にはならない。 ただ、学校への疎外自体を問題にしようとすると、貨幣への疎外を問題にするのと同じで、たいへんラジカル(根本的)な問いになる。そもそ...