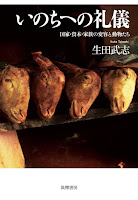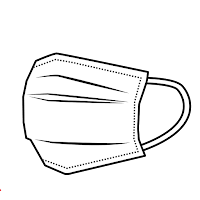「正しさ」と「まちがい」と非対称の関係と

先日、「まちがっているかもしれない」という認識は大事ではないか、という 記事 を書いた。もう少し、このあたりのことについて考えてみたい。 自分は「正しい」と思うのは、とても怖いことだと思う。たとえば、社会運動においても、内部でハラスメントや問題が生じることはあって、でも、自分たちの「正しさ」を維持するために、問題を抑圧してしまうことがある。そういうことを看過してはいけないと思う。 ただ、社会運動の場合においても、何かの被害者の場合においても、立場の弱い側が強い側に向かって声をあげるとき、自分たちは「正しい」と思わなければ、そもそも声をあげることさえできない、ということはあるだろう。世の中の関係は常に不平等で非対称なので、それをフラットに考えることはできない。差別や偏見で「異常」とまなざされていたり、圧倒的に不利な立場に置かれている側が、「まちがっているかもしれない」などと自省させられるいわれはない。むしろ、異常視するおまえらこそが「まちがっている」と見方を反転させる必要がある。 たとえば不登校においても、不登校は「病気」扱いされ、さまざまな人権侵害が公然と行なわれ、子どもたちが苦しめられてきた。しかも、加害している側は「善意」のつもりで加害意識がない。それに対抗する言説として、「不登校は病気じゃない」といったことが語られてきた。病んでいるのは、子どもではなく、むしろ学校のほうではないか、と。そういうカウンターがなければ、「善意」は揺らぐことなく、不登校をめぐる状況は厳しいままだったにちがいない。 しかし、その社会運動をする側が、自分たちの「正しさ」や「善意」を疑わないということになれば、同じ穴のムジナとなってしまう。利敵行為になるから、といった理由で、内部の問題を抑圧することが正当化されてはならないし、「正しさ」を守るために、周囲がそれを擁護するようなこともしてはならないだろう。 「正しさ」は、必要なときはあるとしても、常に問い直されなければならない。 ○ジャスティス ところで、修復的正義について学んでいたとき、ジャスティスという言葉には、「事態を完全にする」あるいは「秩序を健全にする」という意味合いがあるということを知った(ハワード・ゼア『修復的司法とは何か』新泉社2003)。 言うなれば、ジャスティスという理想を置いて、その理想...